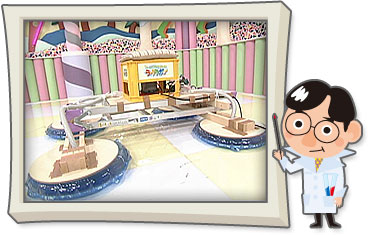■空中で踊る水滴の実験
<材料>
- フライパン
- 水
- 卓上IHクッキングヒーター

<実験>
- 熱したフライパンの上にスポイト等で水を落とす。

《解説》
- フライパンで、水滴が熱され沸騰する。
その時に出る水蒸気が水滴を持ち上げ浮かせている。
(この時、フライパンと水滴の間には、ごく薄い水蒸気の膜で隔てられ直接には接触していない。)
(気体は熱を通しにくいので、水滴はなかなか蒸発しない。)

■身近なもので作った簡単ホバークラフト!
<材料>(カップ麺ホバークラフト)
- カップ麺の容器(深さが浅い物)
- 電池
- モーター
- プロペラ
- 導線×2
<作り方>(カップ麺ホバークラフト)
- カップ麺の容器の底を少し切り取り、空気の取り入れ口を作る。
- プロペラは、推進力を得るために、薄いプラバンなどを貼り、羽根を大きくする。
- 容器の底の中央に、モーターを差し込む穴をあけ、取り付ける。
- プロペラをモーターに付け、テープなどで固定する。
- 電池を容器にテープでつけ、モーターと電池を直列繋ぎになるように導線でつなげば完成。



<材料>(CDホバークラフト)
- いらなくなったCD
- ペットボトル(ふた付き)
- ストロー
- 風船
<作り方>(CDホバークラフト)
- ペットボトルの底にストローが入るくらいの穴をあける。
- ペットボトルのふたにキリなどで直径1mmほどの穴をあける。
- ふたの穴をふさがないように、CD盤の中心に両面テープで貼り付ける。(接着面から空気がもれないよう注意!)
- ストローを5cm程度に切り、ストローに半分くらい風船をかぶせ、テープなどでとめる。
- ペットボトルのふたを閉め、膨らませた風船のストローを差し込み完成。



■人が乗れる手作りホバークラフト
<材料>
- ブロアー
- 脚立(5段1.5mサイズ)
- 浮き輪(直径約60cm) 4個
- 浮き輪用ベニア板(0.8cm×45cm×45cm) 4枚
- ベニア板(脚立のサイズに合わせる)
※脚立の上に乗せる用 - 角材A(3.8cm×6.3cm×120cm) 4本
- 角材B(3.8cm×6.3cm×15cm) 8本
- 流しドレンホース(ジョイント付き) 4個
- プラスチックケース
※ビール瓶ケースなど - ビニール袋 2袋




<作り方>〜浮上装置の作成〜
- ベニア板(厚さ8mm、45cm×45cm)4枚を重ねて中央部にドレンホースの直径に合わせてドリルなどで穴をあける。
- ベニア板の端に厚めの両面テープを貼り、浮き輪を貼りつける。同様に4組作る。
- ドレンホースの口を片方だけ切る。
- ベニア板の穴にドレンホース通し、固定する。
- 床との接触面積を大きくするため浮き輪の空気を少しずつ抜いて調節する。
4つとも同じくらいの接触面積になるようにする。



<作り方>〜木枠の作成〜
- 角材Aの2本の間に角材Bを2本重ねてテープで固定する。
- 同様に2組作る。

<作り方>〜ボディーの作成〜
- 木枠の上に脚立を乗せる。
- ビニール袋の角の2ヶ所を切り、ドレンホースの口を差し込み、ビニールひもなどで空気が漏れないようにしばる。
- ビニール袋同士をドレンホースでつなぎ、これを空気が漏れないようにビニールひもでしばる。
- ホースが通っているビニール袋に穴を1ヶ所開け、送風機の噴出し口を差し込む。
- 脚立の上に板を乗せ、プラスチックケースを被せ、そのなかにコードリールをいれる。
座席の位置は、4つの浮き輪に、均等に圧力がかかる位置に設定する。





≪注意≫
- 床は畳やジュータンの上はダメ。体育館やピータイルのツルツルの廊下がよい。
★番組からのお願い★
「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。
その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。
また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。