■火と酸素の関係
<用意する物>
- スチールウール
- ビーカー 等
- 酸素缶
- ラップ
- ライター 等

<実験方法>
酸素を入れたビーカー(酸素は軽いのでラップなどでフタをして酸素が逃げるのを防ぐ。
※水上置換法を利用するとビーカーの中に酸素をためやすい)に火の付いたスチールウールを入れる。


※水上置換法・・・水と気体を置き換え、水に溶けにくい気体を集める方法。目でみて集まった気体の量を確認できる。(図参照)
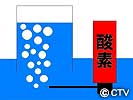
<結果>
スチールウールが勢い良く燃えた!

【解説】
物を燃やすには酸素が必要で、酸素の量によって火の勢いが変わる。
ビーカーの中には酸素が充満していたため、火の付いたスチールウールと反応して激しく燃える。
注:ご家庭で実験する場合は、スチールウールが燃えて火花が飛び散ったり、ビーカーが破損する恐れがありますので十分に注意して下さい
■物が燃える仕組み
物が燃えるためには「酸素」、「可燃物(燃える物)」、「温度(熱)」の3要素が必要である。
すなわち物が燃える3要素のうち1つでも取り除けば火を消すことが出来る。

■ラブラボ!大実験「天ぷら油火災を消火せよ!」
<実験内容>
水、キャベツ、天ぷら油、ドライアイス、を 燃え上がる天ぷら油(天ぷら油の発火温度は330℃)の中に それぞれ入れて火を消せるか調べる。

<水を入れた場合>
天ぷら油の火が爆発的に燃え上がった!


【解説】
燃え上がる天ぷら油に水を入れると、 油の中に一旦沈んだ水が急激に気化・蒸発するため(水の沸点は100℃)、 油がはね上がり火柱が上がる。
<キャベツを入れた場合>
水と同じく天ぷら油の火がさらに燃え上がった!


【解説】
キャベツは水分を多く含んでいるため、水を入れた時と同じく火柱が上がる。
<天ぷら油を入れた場合>
天ぷら油の火が弱まった!


【解説】
油の中にさらに油を入れることで、燃えている油の温度を下げたため火が弱まる。
大量に油を入れると、さらに温度が下がり、火が消える場合もある。

<ドライアイスを入れた場合>
天ぷら油の火が完全に消火された!


【解説】
油の中に沈んだドライアイス(−78.5℃)が油の温度を下げたことと、 ドライアイスから出た二酸化炭素が、天ぷら油の火の周りにある酸素を押し出すことで、 天ぷら油の火元の酸素が無くなってしまい火が消える。
注:これらの実験は専門家の監修のもとで実験しています。絶対にマネしないで下さい。
■ロウソクの消火実験
<用意する物>
- 水槽
- ロウソク(なるべく背が低いもの)
- バケツ
- ドライアイス
- ライター等
<実験方法>
水槽の中に火のついたロウソクを立てる、
バケツの中でドライアイスを気化させておく。
この気体を水槽の中に注ぎこむ。


<結果>
水槽の中のロウソクが全部消えた!

【解説】
ドライアイスを気化させると二酸化炭素が出来る。
これを水槽の中に入れると、二酸化炭素は空気より重いので、
水槽の中の空気(酸素)を追い出し、底にたまるため、ロウソクの火が消える
注:火災が起こった時は消火器を使うか、すぐに消防署へ連絡しましょう!
★番組からのお願い★
「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。
その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。
また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。
