■モノが切れる仕組み
<実験道具>
- 太いパイプ
- 細い針金
- ねん土


<実験内容>
ねん土に太いパイプと細い針金で上から力を加え、それぞれの状態を比べる。
<実験結果>
太いパイプは・・・
ねん土にめり込んでいく。

細い針金は・・・
ねん土が真っ二つに切れた!

【解説】
太いパイプでねん土に上から力を加えると、力が分散(ぶんさん)されて切ることが出来ない。 細い針金で上から力を加えれば、力は分散されず一点に集中されるため切れる。
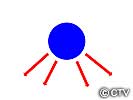

■人類最初の合金「青銅」!
<青銅とは>
銅を主成分とし、スズを含む合金。
■「青銅」を作ってみよう!
<準備するモノ>
- 細かく切った銅板
- スズ
- バーナー×2
- 耐熱ボード
- ステンレス製プリンカップ
- 三脚


<作り方>
- 細かく切った銅とスズをステンレス製プリンカップに入れる。
この時入れるスズの量を調整することで青銅の硬さを変えることが出来る。

- ステンレス製プリンカップをバーナーで上下から熱する。
スズは溶けやすいので先に溶ける(融点231.9℃)。
その後、銅が溶けて混ざり合う。


- 混ざり合った合金を、耐熱ボードの上に流し込む。
すると液体が急激に冷え、固体になっていく。
少し待って完全に冷えて固まれば「青銅」の完成!


※火を扱いますので、火傷や火事には十分に注意して下さい。
■青銅から鉄の時代へ
<はがねとは>
鉄に炭素が混ざった合金。 炭素の割合が多いほど硬くなる性質があるが、弾力がなくなるため折れやすくなってしまう。
■はがねの性質
<実験道具>
- カッターナイフの刃
- バーナー
- 水

<実験・1>
カッターナイフの刃をバーナーで熱して、ゆっくり冷す。

<実験結果>
弾力が出て折れにくくなった(柔らかくなった)。

<実験・2>
柔らかくなったカッターナイフの刃をもう一度熱して、水に浸けて急激に冷やす。


<実験結果>
弾力がなくなり、硬くなった。 熱している時間が長くなり過ぎるともろくなる。


■包丁の切れ味の秘密
目で見ると分からないが、顕微鏡で刃先を見ると、引き切りが出来るようにギザギザなっている。 これはギザギザの刃先1つ1つに切る力を集中させるためである。 使い古した包丁を見ると、刃先のギザギザが潰れて、形もいびつなため、切れ味が悪くなってしまっていることが分かる。 再び切れ味を良くするためには、研磨(研ぎ)が必要となる。 いびつになった刃先を削って鋭角にする事で、元の切れ味を取り戻す。


★番組からのお願い★
「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。
その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。
また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。
