■何で鉄の船は浮かぶ事が出来る?
なぜ大きな鉄のかたまりの船が水に浮く事が出来るのか?
そのナゾを解明するべくラブラボ!が造船所に潜入!
(取材協力:ユニバーサル造船株式会社 津事業所)

- 船は厚さ約2cmの鉄板を使って作られる。
鉄板は切断機を使って様々な形に切り抜かれ、パーツが作られる。




- 鉄板にゆるいカーブを付ける時は巨大なローラーにはさんで曲げ、
仕上げに鉄板の片面を900度前後の炎で熱し、水で急激に冷やす作業を行う。
これは急激に冷やすことによって、表面が縮んでそり返るため。
最後に木の型を当てて、鉄板の曲り具合を確認する。



- 様々な鉄板のパーツを組み合わせて、約100の大きなブロックを作っていく。
ここで作られたブロックは専用の運搬車に乗せて「ドック」と呼ばれる場所へ運び、船へと組み立てていく。
このドックは2つあり、長さ500メートル、幅75メートル、深さ12メートルと14メートルもある巨大なプールのような施設。




- ゴライアスクレーンと呼ばれる大型クレーンを使って、ブロックをドックの中へ運ぶ。
このクレーンは最大700トンまで持ち上げることが出来る。


- クレーンで運ばれたブロックを船の後ろ側から左右対称に組み立てていく。
出来上がっていく船を見てみると、船の中は空洞ということが分かる。
つまり、船は大きな鉄の箱だった!
実は船の中が空洞だということに船が浮く秘密があった!
この秘密を探るために、こんな実験!


<実験内容>
粘土のかたまりを半分に切り分け、一方をかたまりのまま、もう片方をお椀型に形を変えて、それぞれ水の張ってある水槽の中へ入れてみると・・・






<実験結果>
粘土のかたまりは水中に沈んだが、お椀型の粘土は水に浮いた!


<解説>
プールやお風呂に入ると、体が軽く感じる。
これは水面に物を浮かべると、水がもとの水面に戻ろうとして、沈んだ部分と同じだけの水を押しのけるため。
この物体に働く上向きの力を「浮力」と言う。
これと同じで、粘土の重さは同じなのに、形を変えると浮くことが出来たのは、たくさんの水を押しのけ、より大きな浮力を得ることができたため。
船もこの原理で浮いている。

■完成した船はどうやって海にだすの?
遂に完成した船!
この船を一体どうやってドックから海へと運ぶのか?
ラブラボ!が調査をしてきた!

- ドックの中に海水を入れ、船を浮かせる。


- ドック内の水面が海と同じ高さになったところで、ドックと海を隔てている水門をゆっくり倒す。


- 海で待機していたタグボートと船をロープでつなぐ。


- タグボートで巨大な船を海までひき出す。こうして作られた船は大海原へと旅立っていく。

■何で船はひっくり返らない?
<実験方法>
※マストを立てた船の実験装置に井戸田さんが乗り込み、先ずマストの下部へダンベルのおもりをセットした状態で船を傾けると・・・


※マスト・・・舟の帆柱。
<実験結果>
船は倒れず、安定した!
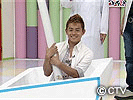
<追加実験>
船のマストにセットされているおもりを上に移動して、傾けてみると・・・

<実験結果>
船が横に倒れてしまった!

【解説】
船が傾いた時、重心が低いと浮力と重力がうまく引き合い、船の傾きを元に戻す「復元力」が働く。
しかし、重心が高いと浮力と重力が、うまく引き合わないため、船は、さらに傾き、転覆してしまう。
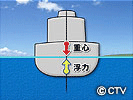
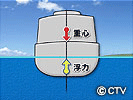
■科学で解明!魔の三角海域の謎
フロリダ半島の先端から、大西洋にあるプエルトリコ。
そして、バミューダ諸島を結ぶ三角地帯はバミューダトライアングルと呼ばれる。
ここでは100年以上も前から数多くの船が、何の痕跡(こんせき)も残さないまま消息を絶つという事件が勃発し、魔の海域と恐れられてきた!
この謎をでんじろう先生が科学の力で解明する!
<実験方法>
水を張った水槽に※エアストーンを置き、船に見立てた器を浮かべる。
そして、エアストーンにつないだチューブの空気入れを勢いよく押すと、大量の泡が発生!!
すると・・・


※エアストーン・・・水槽の中で泡を出す製品。魚を飼う時、基本的に水槽内に酸素を送る目的で使用される。

<実験結果>
器が沈んだ!

【解説】
器が沈んだのはエアストーンから発生した大量の細かな泡により水の密度が小さくなり、器にかかる浮力が小さくなったため。
この原理と同じ様にバミューダトライアングルでは海底からメタンガスなどの泡が大量に瞬時に発生し、それによって船は浮力を失い沈没するという説がある。
この説をメタンハイドレート説という。
■意外なモノで船が進む
<実験方法>
ウレタンフォームで作った船の後ろにしょうのう(防虫剤)をセットし、水に浮かべると・・・




<実験結果>
何と、船が進んだ!!

【解説】
船が進むのは、しょうのうが水に溶けるため。
しょうのうが水に溶けると、水の※表面張力を弱める働きがある。
船の後ろに置いたしょうのうのために後ろの表面張力は小さくなり、前の方は、そのままなので、バランスがくずれ、船は前に引っ張られて進む。
ちなみに、表面張力を弱めるものなら何でも動く。


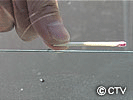
(例)石けんや接着剤など。
※表面張力・・・水の表面には水がお互いに引っ張り合う力が働いている。この力を表面張力という。

★番組からのお願い★
「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。
その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。
また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。
