■カニはどうして横に歩くの?
【実験】
カニの胴体を見立てた平台に、仰向けに寝て足を横に出すとカニの姿に見える。
これで前後左右に足を動かして見ると
左右には動くが前後にはなかなか動かせなかった。

【解説】
カニの脚は胴体の横についているため、関節が横方向に曲げ伸ばしやすくなっている。
そのため前後には動きにくく、横に歩いた方が砂浜や岩の上を素早く移動することができる。


◆カニを使った面白実験!
回転盤の上にカニを乗せ、半球のカプセルをかぶせる。

そして勢い良く、円盤を回転させる。

その後カプセルをとると・・・
カニが前に歩いた!

【解説】
円盤にカニを乗せ、回転させた事によって、カニの平衡感覚が乱れて、前へよろけて歩いた。
■ヒマワリはなぜヒマワリっていうの?
ヒマワリは漢字で書くと「向日葵」。つまり太陽の方向を向いて咲く花という事になる。
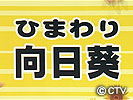
でも本当に太陽の方向に向いて咲いているの?
そんな疑問を解明する為、ラブラボ!取材班がヒマワリ畑へ!
◆太陽に向かって咲くヒマワリ
ヒマワリ畑のヒマワリはどれも同じ方向を向いている。
そこで、太陽の位置と花の向きを調べてみると、ほとんどのヒマワリが東を向いたまま。

しかし、その中でもヒマワリのつぼみだけは太陽の方向を向いていた。


そこで、ヒマワリのつぼみは太陽に向かって動くのかを検証!
【検証】
午前5時30分、観察スタート。

すると、ヒマワリのつぼみだけでは無く茎も葉も太陽を追いかけ動いていた!




【解説】
若いつぼみの時期は、太陽の光が当たらない部分の方が、光が当たる部分より早く成長するため、常に茎が光の方へ向かって曲がる。
その結果、つぼみが太陽を追う動きとなる。
(夕方、太陽に向かい西を向いているつぼみが、朝になると東に向き、元に戻っているのは、夜のうちに、東へ向き直っているため。)
【問題】
ヒマワリの花はいくつある?
【答え】
実はヒマワリは小さな花が千個以上集まった集合花。


■アメンボはどうして水に浮いていられるの?
【実験】
水槽に針金で作ったアメンボとモールで作ったアメンボをそれぞれ浮かべてみると・・・


針金のアメンボはすぐ沈んだのに対し、モールのアメンボは浮いた!


【解説】
アメンボの脚の先には、油のようなものが付いているので、同じように、モールのアメンボには防水スプレーを吹きかけてあった。
それが水を弾いて浮いている。
さらに、毛と毛の間に空気が溜まり、それが水を弾く力を強め、浮いていた。

【実験】
モールのアメンボが浮いている水槽にある液体を入れると・・・

アメンボが沈んでしまった。

【解説】
水槽に入れたある液体は、台所用洗剤。

水槽に台所用洗剤を入れることで、水が油を弾こうとする力が弱まる為、モールのアメンボが沈んでしまった。
◆アメンボの不思議な習性
【実験】
アメンボの習性を探るために用意したのが、電動ハブラシの先に細い針金をセットしたもの。

電動ハブラシのスイッチを入れ、竹竿にぶら下げて、アメンボがいる池へ入れると・・・

アメンボが針金の振動で出来た波紋の真ん中へ集まってきた!

【解説】
アメンボは水面に落ちた昆虫が、もがいてたてる波を感知して捕まえ、エサにしている。
そのため、波紋の中心の針金に集まってきた。
■ダンゴムシはなぜ丸くなるの?
ダンゴムシのお腹は敵に攻撃されると弱いところ。
そこで、硬い甲羅で覆われている体を丸くして敵からお腹を守るから。

ダンゴムシは6本脚の昆虫に対して8本も多い14本もある。
実は虫の仲間ではなく、エビやカニと同じ甲殻類に属している。

◆ダンゴムシの驚くべき能力 ダンゴムシVS井戸田迷路対決!
ダンゴムシと井戸田さん、どちらが速くゴールする?


対決開始と同時に苦戦する井戸田さんに対しダンゴムシは迷うことなくどんどんゴールに突き進んでいく!

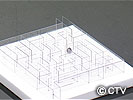
そしてあっという間にダンゴムシのゴール!!でもいったいなぜ?

【解説】
ダンゴムシには交替性転向反応(こうたいせいてんこうはんのう)、つまり交互に自分の進む方向を変える習性を持っている。
対決に使用した迷路は、左右交互に曲っていけばゴールが出来る迷路だった!
■セミはどのように鳴くの?
セミはお腹にある特別な膜を震わせて鳴く。
【実験】
オルゴールの発音器をそのままで鳴らしてみると小さい音しか出ない。

しかしセミのお腹に見立てた木箱に発音器を置いて音を鳴らすと大きな音が鳴った!

【解説】
セミのお腹は空洞になっていて、特別な膜を震わせて出た音が、空洞に共鳴して大きな音になる。
★番組からのお願い★
「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。
その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。
また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。
