■手を使わずに重いコンクリートを持ち上げる!
<準備するモノ>
- コンクリートブロック
- ビニール袋(大きめのゴミ袋)
- 木の板(ビニール袋より大きめのモノ)
- ストロー
- セロテープ
<実験方法>
ビニール袋の口にストローを差込み、その箇所以外は空気がもれないようにセロテープでふさぐ。
次にビニール袋の上に木の板を乗せ、さらにコンクリートブロックを積む。
そして、ストローからビニール袋の中に息を吹き込むと…




<実験結果>
ビニール袋が膨らみ、コンクリートブロックが持ち上がった!

【解説】
袋に吹き入れた息(空気の圧力)は袋の中の全ての部分に等しい強さで伝わる。
これを「パスカルの原理」という。
実は大きなパワーを発揮する「働く車」には、この原理が活かされている。
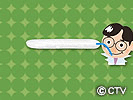
■ショベルカーが一度に掘る土の量はどのくらい?
どんな力仕事もスイスイこなしてしまうショベルカー!
そのパワーは一体どれくらいあるのか?
ラブラボ!ならではの面白実験でショベルカーのパワーを検証!

<実験方法>
ショベルカーが一度に掘り出した土を、スタッフがスコップで全てすくい出す。合計何杯になったかを数え、ショベルカーのパワーを検証する。


<実験結果>
スコップですくい出した数は合計455杯!
さらに、スコップ1杯分の重さを量ってみると約2.3kgだった。



計算してみると…
2.3kg×455杯=1046kg
つまり、ショベルカーは一度に約1トンもの土を掘り出していた!
■ショベルカーはどうして力持ち?
ショベルカーが大きな力を発揮できるのは、「シリンダー」と呼ばれる部分に秘密がある。
その仕組みは操縦レバーを動かすことによって、ポンプからシリンダーの中に油が送り込まれ、その圧力によってピストンが押し出される。
逆に、反対のチューブから油を送り込むとピストンが押し戻される。
これによってピストンが伸び縮みし、同時に大きな力を生み出している。

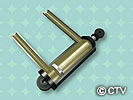
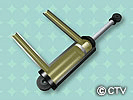
■水鉄砲でわかる働く車の仕組み
<実験1>
細い筒状の水鉄砲と太い筒状の水鉄砲で水を押し出し、それぞれの水の飛び出し方を比べる。

<実験結果>
〔太い水鉄砲の場合〕
力いっぱい押しても、出る水に勢いがない…

〔細い水鉄砲の場合〕
水が勢い良く飛び出した!

【解説】
太い水鉄砲は断面積が大きいので、力が分散してしまい、出る水に勢いがでない。
逆に細い水鉄砲は断面積が小さいので、力が分散せず、勢い良く水が出る。

<実験2>
直径1cmの注射器と直径3.2cmの注射器にそれぞれに水を入れ、両方の先端をチューブでつなぐ。
そして、細い注射器の上におもりを1個の乗せ、さらに、太い注射器の上に先程のおもりと同じ重さのおもりを10個乗せると…



<実験結果>
細い注射器と太い注射器の水かさが等しくなった!

【解説】
太い注射器(3.2cm)の断面積は1.6(半径)×1.6(半径)×3.14=約8cm3、細い注射器(1cm)の断面積は0.5(半径)×0.5(半径)×3.14=約0.8cm3になり、面積の比率は10:1になる。
そこで、細い注射器におもりを1個乗せた場合、太い注射器の方は断面積が10倍あるので、細い注射器からかかる力が10倍になり、おもりを10個置くことで力が均等に釣り合う。
ショベルカーのシリンダーもこの原理を利用して、力を増幅させている。
■働く車はナゼタイヤではない?
<実験方法>
タイヤ付きのブルドーザーの模型とクローラ(キャタピラー)付きのブルドーザーの模型を綱引きさせる。



<実験1>
タイヤ付きブルドーザーが、クローラ付きブルドーザーの力で間単に引っ張られた!

<実験2>
デコボコ道が得意と言われる四輪駆動車と、クローラのブルドーザーでデコボコの道を走り、それぞれの状態を比べる。



<結果>
〔四輪駆動車の場合〕
地面がデコボコのため足元が安定せず、タイヤが上手く地面に接することが出来ないため、スリップしてしまった。


〔ブルドーザーの場合〕
クローラが地面にぴったりと接し、順調に進むことが出来た!


【解説】
タイヤは地面に接する面積が小さいため、悪条件の道では上手く進むことが出来ない。
しかし、クローラは地面に接する面積が大きく、地面にしっかり食い込んで悪条件の道でもスリップすることなく進むことが出来る。

★番組からのお願い★
「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。
その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。
また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。
