■話題のスポット 石見銀山を徹底調査!
今年7月に世界遺産に登録された島根県大田市にある「石見(いわみ)銀山」。
昔、世界で使われた銀の約3分の1が日本の銀だったと言われ、さらに、そのうちの大部分が石見銀山で産出されたていたという。
中世ヨーロッパの日本地図にも石見銀山が描かれていることから、当時の銀の産出量の多さが伺える。
そこで、現在調査中のため、観光客に公開されていない※坑道(こうどう)を特別に調査させて頂いた!


※坑道…主に銀を掘り出すための通路。ちなみに、石見銀山の中には坑道の数が600以上もある!
<調査報告>
坑道の中に入ってみると地面に水溜りが!
これは、銀を掘り出す時に出た湧き水。
坑道では、この湧き水を抜くために斜坑と呼ばれる穴が掘られていた。
斜坑とは地下に向かってななめに掘られた階段状の穴で、25m下の金生坑(きんせいこう)という別の坑道につながっている。
この斜坑で水を抜いたり、作業員が移動したりしていた。


さらに奥に進むこと10分。
ついに銀の鉱脈を発見!


岩の壁にある黒い部分が銀の鉱脈とのこと。
ここから銀を取り出すには、細かく砕いた鉱石を鉛と混ぜ、※キューペルと呼ばれる器に入れ加熱する。
すると、鉛が銀以外の不純物と一緒に溶けだす。
これを冷やすとキューペルの灰によって鉛が吸い取られ、銀だけが残る。
これを「灰吹法(はいふきほう)」と呼ぶ。







こうして取り出された銀が世界中へと運ばれた。

※キューペル…動物の骨の灰を固めた器。

■銀色の金属の中から「銀」を見分けよう
<実験方法>
鉄・アルミニウム・亜鉛・銀の4種類の銀色の金属の中から銀だけを見分ける。

<ステップ 1>
磁石を近づけてみると…

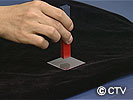
<結果>
1つだけ磁石とくっついた金属があった!
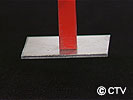
【解説】
この磁石とくっついた金属は鉄。
他の3種類の金属は磁石とくっつかない。
これで、残った金属はアルミニウム・亜鉛・銀の3種類。
<ステップ 2>
重さを比べてみると…
<結果>
1つだけ軽い金属があった!
【解説】
この軽い金属はアルミニウム。
銀と亜鉛はほぼ同じ重さなのに比べ、アルミニウムは半分以下の重さしかない。
これで残りは亜鉛と銀の2種類だけ!
<ステップ 3>
バーナーで加熱してみると…

<結果>
一方が何も反応しないのに対し、もう一方は溶け始めた!

注意:危険な実験のためマネをしないで下さい。
【解説】
この溶け始めた金属は亜鉛。
亜鉛は融点が約420度であるため、バーナーの炎によって溶けてしまう。
これに比べて銀の融点は、およそ950度であるため、バーナーの炎では溶けなかった。
よって、残った金属が銀!
■もっと簡単に銀を見分ける方法
<準備するモノ>
- 入浴剤が混ざっているお湯
- 鉄の板
- アルミニウムの板
- 亜鉛の板
- 銀の板
<実験方法>
入浴剤が混ざっているお湯の中に4種類の銀色の金属を入れると…


<実験結果>
1つだけ急激に黒くなった金属があった!

【解説】
この黒くなった金属が銀。
これは入浴剤に含まれていた硫黄(いおう)の成分が銀とくっつきやすい性質をもっているため。
この硫黄と銀がくっついたモノを硫化銀(りゅうかぎん)と呼ぶ。
この現象によって銀が急激に黒く変化してしまった。
■一瞬で銀をキレイにする裏ワザ
<準備するモノ>
- 鍋
- お湯
- 塩
- アルミ箔
- 黒くなってしまった銀
<裏ワザ方法>
- お湯を沸騰させる。

- 沸騰したお湯に塩を混ぜて食塩水を作る。

- 鍋の底にアルミ箔を敷く。

- この中に黒くなってしまった銀を入れると…

アッという間にピカピカに!

【解説】
銀とアルミ箔が触れた時、この間に電気が流れる。
さらに、食塩水を沸騰させたことで電気の量が少し増える。
この電気によって、銀の表面に付いた硫黄成分などを分解し、銀の黒ずみを取り除いた。
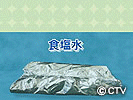
■銀を使ったでんじろうマジック
<マジック方法>
透明な液体の中に板ガラスを入れ、さらにブドウ糖を入れる。
すると、急激に液体が透明から黒に変わった!
そして、しばらくたってから液体から板ガラスを取り出し、板ガラスの片面だけを洗い流すと…





板ガラスが鏡に変わった!

【解説】
透明な液体の中には銀の成分が含まれていた。
その中にブドウ糖を入れると、液体の中にある銀の成分が小さな粒になり、ガラスの表面にくっついた。
そして、板ガラスの片面をキレイに洗い流すことで、ガラスを通して見た銀が反射して、鏡のようになった。
★番組からのお願い★
「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。
その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。
また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。
