■やさしく楽しい!スケート教室
【Lesson1 滑り方の基本】
すべりのポイントはまず立ち方。

両足のカカトをくっつけるように、角度を90度にして立つ。
そして進みたい方向の足に体重をかけ、反対の足で押すように進む。
それを交互に続けると、意外と簡単にすべれるはず!

【Lesson2 簡単な止まり方】
スケートの止まり方はさまざまな方法があるが、足を「ハ」の字にして止まるのが初心者向き。
摩擦力(まさつりょく)が働き、氷がけずれて簡単に止まれます。

■スケートはなぜ氷の上をすべることができる?
スケートリンクに水をまき、水をまいた状態と水をまいていない状態でどっちがすべるかを検証。
【実験】
一定の力でレンガを滑らせ、水をまいた状態と乾いた状態で実験。
これを3回ずつ行い平均を求める。


【乾いた氷】
平均距離 191センチ
【ぬれた氷】
平均距離 233センチ
【結果】
人の足とレンガではすべるときの状況は違うが、ぬれた氷の上のほうが20%ほど距離が伸びた。

※今回の実験は特別な許可を得て、実験しています。
《しかしスケートが乾いた氷の上をすべるのはなぜ?》
【実験】ドリルの先に着けた氷の板をもうひとつの氷の板に回転させながらこすりあわせると・・・
なんと氷がとけた。




【解説】
スケート靴が氷の上をすべるその瞬間、スケートの刃と氷の摩擦熱(まさつねつ)で、氷が溶け、薄い水の膜(まく)ができる。
この水の膜で摩擦(まさつ)が少なくなり、すべることができるといわれている。
実際にすべっているときには、ほとんど肉眼では見えないくらいの薄い水の膜(まく)が張るといわれている。

■スケート靴(くつ)の秘密
【実験】
フィギュアスケート選手とスピードスケートの選手の靴(くつ)を交換してすべってもらうと・・・
2人ともうまく滑れなかった。



【解説】
それぞれの靴(くつ)を詳しくみてみると、フィギュア用に比べ、スピード用の靴(くつ)は刃が長く、幅も細いのがわかる。


フィギュア用の刃は幅があり、安定感がある。
スピード用の刃は、ナイフのようにうすく、よりスピードが出しやすい作りになっている。
スケートの靴は、どうすべるかという目的によって形が変わっていた。
■どうやってジャンプするの?
フィギュア用の靴(くつ)の先端はトゥピックと呼ばれる、ギザギザがついている。

これがジャンプの踏み切りや着地、スピンなどの時に非常に重要になってくる。
【実験】
テニスボールを置いてある角材に向かって転がすとテニスボールが角材に当り、上に飛んだ。


【解説】
横に進もうとする力が縦方向に変わるときにジャンプができる。
そのために必要なのはブレーキ。
横に進むボールを角材に当てる事でブレーキがかかり、その反動で、ボールが飛んだ。




スケートのジャンプをよく見てみると、ジャンプする瞬間に靴(くつ)の先端のギザギザが氷に突き刺さるようにしてブレーキをかけ、ちょうど障害物(しょうがいぶつ)に当たるように、横の力を衝撃(しょうげき)で上に跳ぶ力に変えているのがわかる。


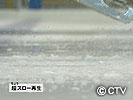
■くるくる回るスピンはどうして目が回らないの?
【実験】
目のまわりを見る特殊カメラをつけ回転し、小沢さんとフィギュア選手を比較。
【小沢さんの挑戦】

目の動きが少し変で、目が回っている。
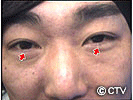
【フィギュアスケート選手】

いつも回転する方向で回ってもらうと、まったく目が回らない。
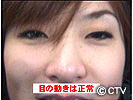
しかしいつもと逆方向で回ってもらうと・・・少し目が回った様子。
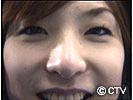
【解説】
頭が回転し続けて止まったばかりの時、体のバランスをつかさどる耳の器官はまだ体が回っていると判断し、情報を脳に伝える。その情報が目にも伝達されて、目は反応を示す。
これが「眼振(がんしん)」という現象。
フィギュア選手が目が回らないのは長い間の練習によって、回転が止まると目の動きもぴたりと止まるよう、脳から目の動きを止める指令がでる訓練が出来ているためと言われている。
逆の方向は訓練されていなかったため、目が回った。
★番組からのお願い★
「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。
その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。
また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。
