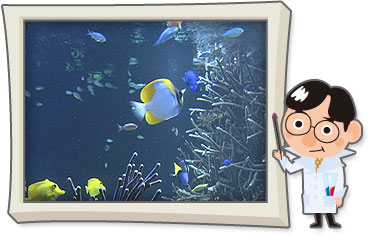■なぜ水族館の中は暗い?
水族館に来てラブラボ!がまず疑問に思ったことは「なぜ水族館で魚のいる水槽(すいそう)の中は明るいのに、お客さんのいる側は暗いのだろうか?」ということ。

これはお客さんが魚を見やすくなるようにという理由もあるが、その他にも理由があった!
実は魚は結構、神経質(しんけいしつ)。
そこで、魚から通路にいるお客さんが見えにくくなるようになっている。
試しに水中カメラを使って、水槽の中からラブラボ!スタッフを見てみると…

ほとんど見えない!!

■まだまだある水族館にかくされた工夫
水族館の水槽は実は厚さ30センチメートル(鳥羽水族館で一番大きな水槽の場合)もあった!

なぜそこまで水族館の水槽は厚くする必要があるのか?
そのナゾを解明するべく、こんな実験を行った!
<実験方法>
6.5リットルの水が入ったバケツと、同じ量の水が入ったホースを用意する。
それぞれの側面に同じ高さになるように穴を開けると…


バケツの穴からは水の出る勢いが弱いのに比べ、ホースの穴からはスゴイ勢いで水が出た!

【解説】
水槽の中に水を入れると、水によって水槽に押す力(水圧)がかかる。
この力は水の量ではなく、深さによって変わる。
バケツよりも深さのあるホースからの方が勢い良く水が出たのはそのため。
族館の水槽はその力に耐えられるように厚くしている。
しかし、それだけの厚みがある水槽はどうやって作られるのか?
ラブラボ!が調査を決行!
■水族館の水槽はどうやって作る?(株式会社シンシ)
- 水族館の水槽は厚み約8センチメートルのアクリルの板から作られる。

- この板を1枚ずつ張り合わせて、厚いアクリルの板を作る。

- 張り合わせたアクリルの板と板の間にアクリルの接着剤(せっちゃくざい)を入れる。

すると、見る見るうちに板が透明(とうめい)になっていく!

これは板の材質と同じアクリルの接着剤を使うことにより、くっついた時に1つの塊(かたまり)となって透明になる。 - 透明になったアクリルの板を水族館へ運び、中で組み立てる。
後は水槽の中に水を入れたら水族館の水槽の完成!
しかし、昔は水族館の水槽はアクリルではなくガラスを使っていた。
なぜガラスからアクリルに変わったのか?
そこでこんな実験!
■水族館の水槽はなぜアクリル?
<実験方法>
2枚の同じ絵の前に、それぞれ同じ厚さのアクリルとガラスを10枚重ねると…

アクリルは透明なままで、変わりなく絵が見えるのに比べ、ガラスは絵の色が変わってしまった!!

【解説】
ガラスは1枚では透明に見えるが、種類によっては薄く色が付いているため、何枚も重ねて厚くすると透明ではなくなってしまい、見えにくくなる。
これに比べアクリルは色が付いていないため、何枚重ねても透明なままでいられる。
水族館の水槽にアクリルが使われているのはこのため。
■水族館の水はなぜいつもキレイ?
水族館の水槽で使われている水は、水族館の地下にある「ろ過装置」によってキレイにされている。
その仕組みは装置の中にある砂の間に水を通すことによって、細かい汚れなどを取り除くというモノ。
こうして水族館の中で水をひとめぐりさせることでキレイにしている。
そのスピードは800トンの水を約1時間半で全て入れ替えてしまうほど!

さらに水槽に付いた汚れは、水族館のスタッフがボンベを背負い、もぐって掃除(そうじ)する。
この時、アクリルの水槽は傷付きやすいため、柔らかいスポンジを使って、少しずつ丁寧(ていねい)に掃除を行う。
そのためスタッフは約1時間半ほど水槽の中に潜り続け、この作業をほぼ毎日行っている。


しかし、一般的に人の肉をも食べてしまうと言われ、凶暴(きょうぼう)な魚と呼ばれる「ピラニア」の水槽は一体どうやって掃除されているのか?
水族館のスタッフに教えてもらった!
■ピラニアの水槽はどうやって掃除されている?
実際にピラニアの水槽を掃除する所をスタッフに見せてもらうと…

ピラニアなんておかまいなしに勢いよく水槽の中に入って掃除している!!


実はピラニアは凶暴な魚と言われているが、意外に神経質な魚で、勢い良く水槽に入れば、逆にピラニアが逃げてしまう。
しかし、実はピラニアより危険(きけん)な魚が水族館にいた!
その魚とは…「デンキウナギ」!!

デンキウナギは600ボルトもの電圧(でんあつ)を出して相手を感電(かんでん)させてしまう恐ろしい魚!
それに対して水族館のスタッフが感電せずに掃除をするために行うことは…
まず網(あみ)を水槽の中に入れデンキウナギを刺激(しげき)し、放電(ほうでん)させる。
そして、ある程度デンキウナギが放電したら、離れた所を見計らって…

掃除!!!!

さらに、デンキウナギが掃除中に近づいてきたら…

逃げる!!!!

こうして感電することなく掃除を行える。
しかし、実はこの方法も確実(かくじつ)ではなく、感電してしまうことも…
水族館のスタッフの気持ちを体感(たいかん)するため、スタジオにもデンキウナギが登場!!
■デンキウナギの電気を体験しよう!
<実験方法>
スタジオに用意されたデンキウナギ(?)が入っている容器に手を入れると…

ビリビリビリビリ!!!!
感電してしまった!!
【解説】
実はこのデンキウナギはでんじろう先生が粘土(ねんど)で作ったモノ。
このデンキウナギが入った容器の両端にも電極(でんきょく)が付いていて、この中に手を入れると感電してしまう仕組み。
ただし、この仕掛けでは実際のデンキウナギが放つ600ボルトもの電圧は出ない。
注意:この実験は専門家の指導のもと行っています。絶対に真似しないで下さい。
★番組からのお願い★
「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。
その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。
また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。