でんじろう先生のはぴエネ!毎週土曜 午前11時35分~ 私たちの生活で様々な役割を果たしているエネルギー。身近だけど、意外と知らないエネルギーをでんじろう先生がおもしろ実験で徹底解明します!
2014年6月7日放送 第271回
「振り子の秘密」
6月10日は「時の記念日」。
時計の仕組みで最も重要なのは「正確に一定のリズムを刻む」こと。
今回は「振り子時計」の振り子に迫ります。

(1)
紐の長さが同じ、重りも同じ重さの振り子が3つあります。
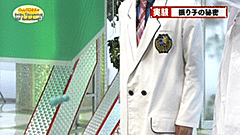
(2)
3つを同じ高さから揺らすと・・・当然、同じように揺れます。

(3)
そこで、この3つのうち、2つの重りをくっつけます。
これで、片方の重りは2倍の重さになりました。
では、この二つを同じ高さから揺らすと、どんな違いがでるのか・・・
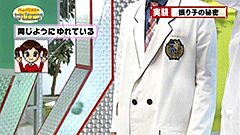
(4)
同じように揺れている!
振り子は重さに関わらず周期は同じなのです。
実は、振り子の周期を変えるには、紐の長さが重要なのです。

(5)
ここに紐の長さが少しずつ違う振り子があります。
これを、同じ高さから揺らすと・・・
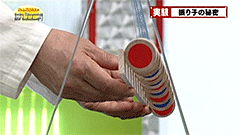
(6)
このように、長さが違うと揺れる周期が変わります。
紐が長ければ、周期は長くなり、紐が短ければ、周期は短くなります。
この振り子の原理を発見したのは、ガリレオ・ガリレイ。
さらに、この原理を応用して、クリスティアーン・ホイヘンスが1657年に発明したのが「振り子時計」なのです。
★番組からのお願い★
「はぴエネ!」は大人から子供までを対象に、身近なエネルギーを理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。
その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。
特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。