でんじろう先生のはぴエネ!毎週土曜 午前11時35分~ 私たちの生活で様々な役割を果たしているエネルギー。身近だけど、意外と知らないエネルギーをでんじろう先生がおもしろ実験で徹底解明します!
2020年6月6日放送 第583回
「ロウソクの科学」
ロウソクの科学第3弾。今回はロウの性質に注目。
ロウソクは、一度火をつけると安定して燃えますが、その原材料である『ロウ』はどれぐらい燃えやすい物質なのか?
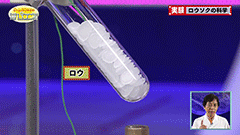
(1)
試験管にロウが入っています。温度をはかりながら、ロウを加熱していきます。

(2)
ロウはおよそ60℃から溶け始め、液体になります。さらに、熱していきます。

(3)
液体になったロウの温度は250℃をこえました。ロウに火を近づけます・・・まだ、燃えません。
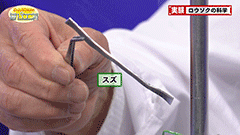
(4)
金属の『スズ』を熱したロウの中に入れると、あっという間に溶けてしまいました。金属が溶ける温度になってもロウは燃えないのです。

(5)
さらに熱して300℃を超えました。もう一度、火を近づけます・・・やっぱり、燃えません。

(6)
でも、この溶けたロウを水に入れれば・・・激しい反応がおきました。こんな風になるほど高い温度にしても、まだ火はつかないのです。
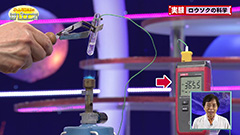
(7)
安全に実験を進めるため、少しロウの分量を減らして、さらに熱していきます。360℃を超えました。これに火を近づけると・・・

(8)
ようやく火がつきました。つまり、火がついているロウソクの先は、かなり高い温度になっているわけです。
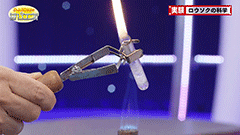
(9)
この火がついた状態で、ロウをバーナーから遠ざけると、火は小さくなり、また、バーナーに近づけると、火は大きくなります。つまり、ロウの温度によって炎の大きさが変わってしまうのです。

(10)
しかし、ロウソクは一度芯に火をつけると、炎の大きさはほとんど変わらず、安定して燃え続けます。ロウソクは、簡単に安定した灯りを長時間作り出せる、とても優れた発明だったのです。
★番組からのお願い★
「はぴエネ!」は大人から子供までを対象に、身近なエネルギーを理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。
その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。
特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。