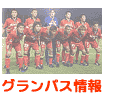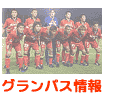新時代の「新星」たち、入団
―歴史の変遷を象徴する5人の若者たち―
|
Jリーグ発足10年目という節目の年だった2002年、悲願のリーグ優勝に、またも届かなかったグランパス。
W杯イヤーを終え、全てにおいて新しい時代に入った日本サッカー界の流れが、19日のグランパスの新入団選手の発表記者会見の場でも現れた気がした。 |
この日会見に臨んだ選手は5人。24日にはレンタル移籍が終了し復帰する選手や他のクラブから移籍してくる選手5人の会見が行われる。すなわち今回グランパスは10人もの”新戦力”を加えることになる。それはまた、同じ数の人間がクラブを去っていくことにつながっているのだが、ベルデニック体制2年目、本格政権として今度こそ結果を残さなければならない状況を考えれば異常なことではないだろう。
注目すべきは今回入団した5人の新人選手たちの「経歴」である。ここにこの10年の日本サッカーの歩みの跡が記されていたし、これまでのグランパスに入団してきた選手たちとは異なるものが存在していたと実感した。
|

新時代の中で育った若者たちの船出だ
|
青山学院大から入団するMF北村隆二(後列左端)は神奈川の逗葉高校の出身。2年生の時、全国高校サッカー選手権大会に初出場でベスト8に進出した。当時W杯初出場を決めた立役者として人気沸騰中だった岡田武史元日本代表監督の早大時代の先輩・小柴健司監督の標榜する奔放なサッカーで勝ちあがり注目を集めた。卒業後即プロ入りはできなかったが、Jリーグ発足以来「取り残された存在」といわれた大学サッカーで実力をつけ、去年6月に練習に参加して認められて入団した。高校−大学という、”かつての”アマチュアサッカーの王道の中から育まれた選手だ。
左サイドのスペシャリストとして期待の高い渡辺圭二(後列右端)は静岡の沼津学園の出身。サッカー王国静岡とはいえ、全国的には全くの無名の存在だ。かつての日本の高校生年代の育成は全国規模の系統だった育成プログラムがなく、高校サッカーの監督という”個人”の能力に依存している状況が強かった。そんな中であれば渡辺のようなプレーヤーは生まれなかっただろう。しかし今はナショナルトレセン制度を中心に、全国にの育成プログラムの網が張り巡らされている。才能を育んでいく土壌の底上げの中で、渡辺は自らの武器を着々と伸ばし、ベルデニックの目にとまりテスト入団を果たした。
U−16から各年代の日本代表を経験し、世界を視野に入れる大物司令塔候補、平林輝良寛(=きよひろ、前列右端)は稲沢FCを経て、ジュニアユース年代からグランパスの下部組織で育った。生粋の「クラブ世代」の選手である。学校教育の中のサッカーとは全く接点を持つことなくその才能を伸ばしつづけた、現代の日本サッカーのサラブレッド。それゆえに本人には大きな期待とプレッシャーがかかっていることだろう。クラブとしてもトップチームで絶対に結果を出させたい存在である。
同じユース出身だが、スピードと突破力が持ち味の森敬史(前列中央)はやや道のりが違う。高3の夏休みの段階ですでに愛知学院大学へのスポーツ推薦での進学が決まっていた。普通で行けば当然春からは大学サッカー界でプレーするはずだったが、後からトップチーム昇格の打診があったのだ。大学に籍を置きながらプロとしてプレーする、キャリアのクロスオーバーを選択したのだ。これもアマとプロの垣根のない交流という流れが生み出したプレーヤーということになる。
高い身体能力と正確なロングフィードを持つDF深津康太(前列左端)は千葉県の流通経大柏高の出身。高校サッカー選手権に出場歴はない新鋭校だが、関東では既に強豪校としての地位を確立している。習志野高を全国制覇に導いた名将・本田裕一郎監督を招聘し、今年の高校選手権を制した市立船橋などと日々切磋琢磨をしている学校だ。クラブチームという育成の「王道」が結果を残す中で、競技性と育成を学校教育の中で両立させるという難しい課題を背負う高校サッカー界の昨今の積極的な動きの中で育まれてきた選手。彼もまた、この10年の日本サッカーの流れの中から生まれてきたプレーヤーといえる。
これまでグランパスが得意としてきた、実績や話題性豊富な選手を、資金力と環境のよさをアピール材料にして獲得するというやり方で獲得した選手たちではない。それゆえに、これまで以上にクラブとしてのポリシーが問われるものになった。クラブの、そして日本サッカーの進化の過程を象徴する5人には、待ちうける大きな未来に向かって前進してもらいたいと切に思う。
取材:大藤晋司
[2003.1.20]
|