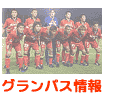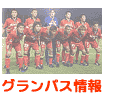チームの新たな“顔”を作る若者達の躍動
―戦力の融合を進める戦い―
|
開始早々、手もとの時計では45秒だった。前回の対戦で4点をたたきこまれ、怖さが刷りこまれていた仙台の選手のイージーミスをついてウエズレイの右足がペナルティエリアの外で炸裂した。あっさりと奪った先制ゴール。しかしそこからが、それまでの殻から抜け出そうともがくチームの新たな動きの始まりとなったように見えた。
|
8連勝が止まったあと4連敗。これまでグランパスというチームが持ち続けてきた“もろさ”がやはり今回も顔を見せた。あえぐようにして広島戦で連敗をようやく止め、絶好調の浦和には必死で食い下がってあわやという試合を演じてみせた。このまま終わるわけにはいかない。なにかをつかみたい。つかんだところを見せて欲しい。23日の仙台戦は、優勝という夢が遠のいた今、選手とサポーターが望むもの、同じものが求められていたはずだ。その意味でこの夜は、簡単すぎるほどに早くに奪った先制点からが興味深い試合だった。
このままポンポンと追加点が入ったら、ある意味ではこれまでのグランパスと同じだった。自分達がアドバンテージをとって精神的に優位にたった試合では圧倒的な強さを見せる。しかし重圧を受けなければならない厳しい試合展開になったときは別のチームのようなバランスの悪さを露呈する。そんなこれまでのチームカラーの“良いほう”が出ておしまい、という試合になったかもしれない。しかし仙台が虎視眈々と狙い続けた、高い位置でインタセプトしてからのアーリークロスでマルコスの決定力を生かす、というパターンが前半36分にはまって同点に追いついたことで、「変容」が求められた。“良いグランパス”と“悪いグランパス”、二つの顔のうちどちらが顔を見せてもおかしくない拮抗した状況になり、チームという生き物は自分でどちらかの顔を選ばなければならない状況に追いこまれたのだ。
|

正念場の若手が「活気」を与えた
|
どちらの顔を選ぶのか、振り子のようにチームの表情がゆれる状況に答えを出したのは、“伸び悩み”と評されて屈辱に耐えてきた若手選手だった。韓国・釜山で、日本サッカー史上初のアジア大会銀メダルをもたらしたU−21日本代表。彼らと同世代で、市立船橋高校時代は他の誰よりも脚光を浴びてきたFW原竜太。入団して3年目。勝負の年と位置付けられながら、途中入団のヴァスティッチにポジションを奪われ、”第3のFW”に甘んじてしまっている。同年代の仲間達の快挙に加わることができず、チームの中での戦いを余儀なくされていた21歳は、ひたむきに流れを呼び寄せようと動き続けた。持ち前のウラへ飛び出すスピードだけでなく、172センチという小さな体ながらポジショニングとボディバランスでポストプレーも積極的にこなす。「イヴォ(ヴァステッチ)がいないから、ピチブー(ウェズレイ)がいつもより下がってボールを出すプレーが多くなるとは思ってた。その分、僕のプレーにミスがないようにしないと、得点のチャンスが広がらないとは意識していた」
FWとしての総合力を示そうという決意は、プレーの随所に見られていた。
もう一人、“熱さ”を全面に出した若手が、後半12分から投入された滝沢だった。中谷が左膝手術で長期戦線離脱をしている中、左サイドのレギュラー獲得の絶好のチャンスを迎えながら精彩を欠き、「チーム最大の弱点」とまでいわれるサイド攻撃の弱さの責任を背負ってスタメンから外れることが多くなっていた22歳。彼もまた、「このままではいけない」という危機感と反骨心を抱いてピッチに立った若手選手だった。
勝ち越しゴールは、このコンビから生まれた、原が中央でドリブル、DFをひきつけてウエズレイにパス、周囲を良く見て前に送られたパスに反応したのが滝沢。その後前にボールを出したがこれが大きく、あわやゴールラインを割るかと見えた。しかし滝沢はあきらめなかった。本当に「身体全体で」という表現がふさわしい、飛びこむようなプレーで折り返すと、ファーサイドに走り込んでいた原がこれまた体を投げ出すようなダイビングヘッドでゴールを決めた。これまであまり見られなかった、それ故に試合全体に物足りなさを感じることの多かった、若い選手のダイナミックなプレーが、チームの表情を決定付けた。
3点目のウェズレイのPKも、それを呼びこんだのは左サイドを疾走した滝沢のドリブルだった。「もうそろそろボールを離すんじゃないか」「もう出すだろう」そんな思いが2度3度観客席に走る中、滝沢は強引に前へ行き、DFと勝負した。若さが持つ特権、それを滝沢は惜しげもなく使っていった。こうした姿に、勝利という結果だけではない満足感を覚えたサポーターは多かったはずだ。優勝も遠のき、降格もない。そんな中で見たいものは、未来への“芽生え”だ。結果を伴なう未来への萌芽。それが一つでも多く出ることことが、チームの“いい顔”を創っていくことになる。
「前節の浦和戦、使ってもらったのにチームとしては勝ちきれなくて、危機感は感じていた。自分から仕掛けていくタイプの僕が途中から入ると生きるなというイメージは持っていた。でもそれがいいことだと思っちゃいけない。本当は最初から出なきゃいけないんだから。」
照れたような表情で試合後の滝沢は話した。しかし言葉には力がこもっていた。チームがこれまで変えられなかった“顔”を一気に変えていけるような、大胆で、躍動感があるプレーを、彼らからもっと見たいと思った。
26日の京都戦。3連敗中の京都相手に先制しながら粘られて勢いを保ちきれず延長で敗れた。安定感は未だにチームの中に根付いていない。しかし、問題は未来への「芽生え」のプレーを感じさせるプレーがどれだけ見られたかだ。その視点を今後は大事にしたい。
取材:大藤晋司
[2002.10.26]
|