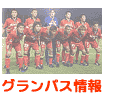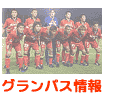苦しみながらのホーム瑞穂7連勝
―戦力の融合を進める道は険しい―
|
この日の瑞穂は、寒かった。
11月9日。FC東京戦。真冬を思わせる冷たい空気、どんより曇った空、絶え間なくふき続けた寒風。どれもこの時期の試合観戦には辛さを感じさせるものだった。そして、ピッチ上で展開されたものも、ときに辛さを感じさせる「寒い」ものとなってしまった。 |
出場停止のウエズレイ、負傷のヴァスティッチという“絶対的な”2枚看板を失ったチームがどんな戦いを見せるのか、優勝という目標がなくなり、「積極的に若い選手を使う」とベルデニック監督が明言した中で迎えた試合は、若い選手たちの縦横無尽にピッチ上を走りまわるシーンで、寒さを吹き飛ばしてくれるはずだった。
ボランチにルーキーの山口慶、FWは21歳の原と「黄金」ルーキー片桐淳至の2トップが起用され、そうした期待は高かった。それだけにひときわ寒さが身にしみた。
|

“荒々しさ”こそ若さの特権だ
|
これはグランパスの長年の課題というべきものだが、戦術を忠実にこなそうという気持ちが強すぎるのか、各選手の「顔を出す」動きが圧倒的に少ない。だからボールが手詰まりしなかなか前へ向かっていかない。相手に攻めこまれる危険な時間は少なくても、それと同じ、時にそれ以上に相手ゴール前にボールが行くことが少ない。それはすなわち、スタジアムの観衆の心が動く回数が少なくなることを意味する。悲鳴も、歓声も、あげたいという期待をもって足を運んでいるサポーターが、そのどちらもあげるチャンスがなく、ただボールの動きを追うだけの時間が長く続くのだ。心が動く機会がないままこの寒さにさらされるのは、ことさらにこたえた。
プロのフットボールを見に行く以上、洗練された高度な、それを実行するために見につけられた高度な技術が展開されて欲しいとは思う。だが、サポーターがスタジアムに足を運びのはサッカーの何に魅せられているからか、それは「ゴールへ向かう情熱」のはずだ。戦術、技術のワクを越える情熱が、フットボールの根源なのではないか。(これはこの国の代表を率いる指揮官も指摘している)まずゴールへ向かう情熱ありき。若い選手がチャンスをもらっている今こそ、もっと見たいと思う。
終了間際に原が渾身のヘッドを決めホーム瑞穂でのリーグ最終戦勝利、そして瑞穂7連勝という結果は残せた。ただ、ゴールの瞬間に周囲を包んだ空気は「歓喜」というより「ゴールへの情熱」をやっと見られた「安堵」のように感じられた。
「冷静と情熱の間」という映画があったが、サッカーとはまさに「冷静と情熱が錯綜」することに魅力があると思う。しかしあくまで“情熱”は“冷静”を上回る比率で展開されるべきもののはず。残りわずかな試合の中で、それがミスとなって現れてもいい、もっともっと“情熱”を見せてほしいと思った。
取材:大藤晋司
[2002.11.9]
|