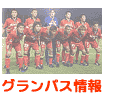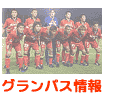大観衆が見届けた「現実」と「課題」
―史上ワースト記録に終わったステージの最終戦―
|
3万5千人以上の観衆が、それを見届ける“証人”だった。
Jリーグ発足10年という記念の年を締めくくる11月30日の第2ステージ最終戦は、チームとして初めて迎える「優勝チームをホームに迎えての消化試合」となった。 |
史上初の快挙である2ステージ完全優勝を果たした磐田。そしてその磐田の完全優勝を阻止する最右翼と第2ステージ開幕前は予想されながら、チームワースト記録の13位に終わった名古屋。3ヶ月を経て迎えた最終節、両チームに残った結果は対照的すぎるものだった。そして、そのあまりにも大きい結果の差を見届ける役を担ったのが、この日豊田スタジアムに足を運んだサポーターだった。
若手中心のメンバーで明日を模索し続けたここ数試合だったが、優勝チームへの敬意と身自らのプライドをかけベストメンバーで臨んだ名古屋。しかし「横綱相撲」で勝ちつづけた磐田は、そんな名古屋に対しても真の強さを見せつけた。
|

勝者と敗者、厳しい現実がそこにあった
|
史上最年少の得点王となった高原、ベテランらしい落ち着きと無駄のない動きを見せた中山、日本代表の常連としての風格が漂う福西、円熟のパスワークを見せた藤田、激しさと巧みさを備えた鈴木、田中、大岩のDF陣、他チームなら紛れもないレギュラーFWの川口、ジブコヴィッチの両サイド、名波、服部を欠きながら、この戦力の充実度はあっぱれだ。
しかし、見せつけられた「真の強さ」とはそうした個人の強さだけではなかった。一人の選手がボールを持つ、いや、ボールを持つ前から、近くの選手、遠くにいる選手が、一斉に「次の動き」「もう1つ次の動き」へ向かって動き出す。その全体の動きの鮮やかさは、美しいとさえ感じるものだった。キックオフからタイムアップまで、「先を読んで全員が動く」連動性は途切れることなく続いた。
対する名古屋は、ボールを受けてから次のプレーを考え始める、故に相手の防御に先につかまり、絶対的な破壊力の2トップ(ウエズレイ、ヴァステイッチ)へのボール供給回数が決定的に少なくなり、「ゴールを狙う」というサッカーの最大の楽しみを、赤く染まったサポーター席の人々は享受することはできなかった。
「ゴールへ向かう情熱」を感じることのできないフラストレーションを、サポーターはシーズンを通して感じざるを得なかった。しかもそれは、今年だけに限ったことではなく、過去何年にもわたり、繰り返された光景だった。
とはいえ、自慢の2トップが見せた2つのゴールはどれも国内レベルを超えた見事な内容のもの。「そこまでの過程」さえ整えば十分に観客に歓喜を与える潜在能力があることを示したという収穫もあった。
見えたものと、見せつけられたもの。巨大スタジアムで繰り広げられた消化試合の意味をかみしめることが、次なる夢の始まりであると信じたい。
取材:大藤晋司
[2002.12.2]
|